前回の記事“まずは基本について理解しよう!話題の「クローン犬」について~第1段~”では、クローン動物の概要をお話ししました。そこでの重要なポイントは、次の2つでした。
・話題のクローン犬は、体の一部から細胞を取って作る、体細胞クローン
・クローンは、ゲノム(遺伝情報)が同じ
今回はクローン動物や、自然界のクローン生物の話を紹介し、クローン犬の是非や、時折話題となる人は“氏か育ちか”について述べます。
■三毛猫のクローン

三毛猫から作ったクローンが二毛猫になったという話は先回も紹介しました。こちらの記事では、写真aからのクローンが写真bの仔猫(代理母と一緒に映っています)。
猫に限らず動物の毛の色と配色は、クローンでもカーボンコピー(まったく同じ)にはなりません。
■女王蜂と働き蜂はクローン

卵を生み、体が3倍にも大きくなり、寿命も30倍以上は違う女王蜂と働き蜂は、実はクローンです。ゲノムが同じクローンの幼虫の中で、ロイヤルゼリーを得た幼虫が
■オランダ飢餓

第二次世界大戦時のオランダを中心とした調査で、飢餓にあった母親から生まれた子どもは、中年期以降、統合失調症、糖尿病、心臓病、メタボリクシンドローム、乳がん等になりやすいことが分かっています。母体の中で、もともと存在する遺伝的な素因に、飢餓が影響を与え
■育児の違いによる脳内の構造の変化

有名な実験ですが、子育てが上手(毛繕いが好き)なラットの子どもは、やはり子育てが上手です。子育ての嫌いなラットの子どもは、子育てが嫌いです。しかし、子育ての嫌いな親から生まれた子を、子育ての好きな親に育てさせると、子育てが好きになります。
この一連の現象は、子育ての好き嫌いは遺伝的であるが、育て方に
■エピジェネティック

4つのお話をしましたが、たとえクローンであっても、毛色が違ったり、栄養状態によって運
この後天的要因は、遺伝子発現のオン・オフのスイッチを入れるメカニズムと考えられ、エピジェネティック(ジェネティックは遺伝子・学、エピは上のという意味)と呼びます。
つまり、遺伝子が存在しても、エピジェネティックな作用で遺伝子が発現しなくなる現象があるということです。
■クローン犬の是非

人の身長のように、エピジェネティックな要因よりもジェネティック(遺伝的)な素因が大きいものもあります(※6)。チワワにたくさんカルシウムやビタミンDを与えても、G・レトリバーには絶対になりません。そういう意味では、クローン技術で体格が似たものは作製できます。
しかし、クローン犬といえども、エピジェネティックな影響により、性格や行動がまったく同じ犬には成長しないということは明らかです。クローン動物の作製成功率は2~5%と考えられており(※7)、その精度の低さも未解明です。代理母犬の負担も考えると、クローン犬作製の是非を立ち止まって考えるべきです。
よく話題となる“氏か育ちか”に関して、クローン生物の話や生育過程における影響のデータから言えることは、“氏も育ちも”ということです。いや、こと人間に関しては、nurture over nature(氏より育ち)かもしれませんね。
【関連記事】
※ 飼い主は犬猫の保険に入るべき?気になる「ペット保険」について獣医師が解説
※ これだけは知っておきたい!犬の「免疫」の基本と免疫系の疾患について
※ 鼻がカサカサ…そのままで大丈夫?「犬の鼻が乾燥する原因」を解説
※ 犬の健康のために知っておきたい!正しい運動量のポイント3つ
【参考】
※1 仲野徹(2014)『エピジェネティックス』岩波新書.
※5 鵜木元香(2016)『生まれつきの女王蜂はいない』講談社.
※6 太田邦史(2013)『エピゲノムと生命』講談社ブルーバックス.
※7 石野研究室ホームページ
【画像】
※ Kachalkina Veronika, Kristi Blokhin, kosolovskyy, Suzanne Tucker, Kirill Kurashov, Likoper, Grigorita Ko / Shutterstock
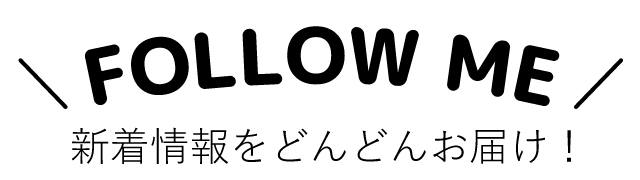




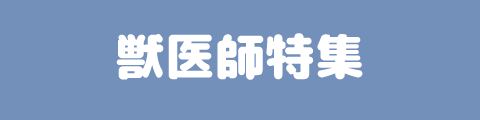

戻る
みんなのコメント