怖い病気を防ぐために必要なワクチン。さまざまな情報があるため、実際どうしたらいいのか困ってしまう飼い主さんもいらっしゃるかと思います。今回は犬のワクチンの接種時期や打たなければいけないワクチン、ワクチンで防ぐことのできる病気についてお話しします。
■絶対に打たなければいけないワクチンは?

世界小動物獣医師学会が定めた、必ず打たなければいけないワクチンは「コアワクチン」と呼ばれ、どこに住んでいてもどのような生活をしていても全ての犬に打つべきワクチンのことを指します。このワクチンに含まれる病原体は全世界にあり、感染すると命に関わることがあります。
例外として、この定義には当てはまらなくても、法律で摂取が決まっていることで必ず接種すべきワクチンとして扱われているものもあります。日本では狂犬病ワクチンがそれにあたります。
これに対して、ノンコアワクチンは生活環境によってリスクとメリットを考え接種するかどうかを判断するワクチンです。
犬のコアワクチン
・犬ジステンパーウイルス
・犬アデノウイルス
・犬パルボウイルス2型
・狂犬病ウイルス
日本では法律でワクチン接種が定められている病気。全ての哺乳類に感染し発症すると効果的な治療法がなくほぼ100%死亡する感染症です。現在日本には存在していませんが、存在している国との国交があり狂犬病侵入防止の為、法律で年に一回の接種が義務付けられています。
犬のノンコアワクチン
・犬パラインフルエンザウイルス
犬パラインフルエンザウイルスは、犬の風邪の病原体です。犬がたくさんいるところによく行く、ペットホテルによく預けられる犬は接種を検討するのが良いのではないでしょうか。
・ボルデテラ・ブロンキセプチカ
伝染性の呼吸器疾患であるケンネルコフの病原細菌です。単独感染では一般的に症状が軽く、症状を示さない犬もいます。他のケンネルコフ病原体と複合感染した場合、症状が強くなる可能性があります。
・レプトスピラ
主にねずみの尿から感染する人獣共通感染症です。ねずみの多いところをはじめ、河川や沼の近く、屋外で生活している、アウトドアによく行く、猟犬であるなどの条件にあてはまる子は接種を検討すべきでしょう。
■ワクチンはいつ打つべき?子犬の場合、成犬の場合は?

ワクチン接種時期は子犬、成犬で異なります。
その理由は、母犬からもらう免疫力の持続期間にあります。この免疫力が子犬に十分ある内はワクチンを接種しても効果がありませんが、免疫力は永久に続くものではないため、無くなってしまうと病気に感染してしまいます。
また、母犬からもらった免疫力の持続期間は個体差が大きいことが分かっており、兄弟姉妹犬の間でも大きなばらつきがあることがあります。この免疫力は生後8~12週齢までにワクチンが作用できるレベルまで下がると言われていますが、まれに12週齢を過ぎてもワクチンに反応できない子もいます。
この時期については、一般的な診察で確実な予想をすることはできません。そのため、子犬のワクチン接種の場合は母犬からもらった免疫力がいつなくなっても病気を予防できるように複数回ワクチンを接種し、免疫力がなくなって病気にかかりやすい時期を絶対に作らない! ということが重要なのです。
■子犬のワクチン接種間隔

世界小動物獣医師会のワクチン接種ガイドラインでは、狂犬病以外のコアワクチンは生後6~8週齢で1回目のワクチンを接種し、16週齢またはそれ以降まで2~4週間隔で接種。その後、半年から1年で再接種を行い、それ以降コアワクチンについては3年以上ごとに接種を行うことを推奨しています。
特に、16週齢以降の接種が重要となっています。また、再接種に関しては免疫力を強化する意味もありますが、それまでのワクチン接種に十分反応しないで免疫力がつかなかった犬に確実に免疫力をつけさせるという意味があります。そのため、世界小動物獣医師会は確実な感染症予防の為に半年~1年の間のなるべく早い時期に接種することを推奨しています。
狂犬病ワクチンに関しては、法律で定めている接種法を分かりやすく説明すると、子犬の場合は生後91日以上で接種、生後91日以降に飼い始め未接種または接種歴不明な場合は飼い始めてから30日以内に接種、以後1年ごとの接種が義務付けられています。
■成犬のワクチン接種間隔

子犬期のワクチンプログラムが完了している場合(半年~1年の再接種まで)
コアワクチンの場合
狂犬病以外のコアワクチンに関しては、3年以上ごとの接種が推奨されています。ただ、免疫力の持続に関しては使用しているワクチンの種類や個体差、治療でステロイド薬を使用しているなど状況によっても変動してくるため、3年に1度と決めつけるのではなく免疫力があるか調べる抗体価検査をするのも一つです。
日本でも、病院によっては年に一度検査をして抗体価が低ければ、ワクチンを打ち十分に抗体価があるようならその年は見送るという方法を提案している病院もあります。不要なワクチンを打たなくて済むので、犬の体にとっては一番優しい方法です。しかし、検査代の分お金もかかるため、かかりつけの獣医師さんにどういった方法が愛犬に合っているか相談してみるのもひとつです。
ノンコアワクチンの場合
ノンコアワクチンに関しては基本的に1年ごとの接種が推奨されています。
ボルデテラに関しては、高リスクの場合、それを上回る頻度での接種も実施している事例があるようです。犬の生活環境、体調等を考慮してリスクとメリットを比べ接種するかしないかを主治医と相談しましょう。
成犬になってから初めてワクチンを打つ、また今までのワクチン接種歴が不明な場合
ノンコアワクチンに関しては、種類によって1回接種で免疫を得られるもの、2回接種の必要なものがあるのでかかりつけの獣医師さんと相談しましょう。
・犬パラインフルエンザウイルス・・・1回接種、以後1年ごとの接種を推奨。
・ボルデテラ・・・2~4週間隔で2回接種、以後1年ごとか高リスクの犬についてはそれ以上の頻度での接種を推奨。
・レプトスピラ・・・2~4週間隔で2回接種、以後1年ごとの接種を推奨。
また、ワクチンに関してはそれぞれの動物病院で用意している種類が異なります。どの種類のワクチンを接種するのが犬にとってベストか獣医師さんとよく相談し、何種のワクチンをどの間隔で打つのか決めましょう。
ワクチン接種では、副反応と呼ばれるアレルギー症状が起こることも稀にあります。不要なワクチンを打たないためにも、抗体価検査などを活用しながら上手にワクチンを接種して愛犬を感染症から守りましょう。
※ 本サイトにおける獣医師および各専門家による情報提供は、診断行為や治療に代わるものではなく、正確性や有効性を保証するものでもありません。また、獣医学の進歩により、常に最新の情報とは限りません。個別の症状について診断・治療を求める場合は、獣医師や各専門家より適切な診断と治療を受けてください。

【関連記事】
※ 子犬にワクチンはいつ接種する?種類は?獣医師がワクチンの疑問を徹底解説
※ 「ノミ」の被害はたくさんある!? 愛犬を守るために知識を深めよう
※ あなたの愛犬は大丈夫?今すぐ実践したい「蚊・ノミ・ダニ」ワクチン以外の対策
【参考】
※ 犬と猫のワクチネーションガイ
【画像】
※ Iryna Kalamurza,WIRACHAIPHOTO,Sergey Mikheev,all_about_people,Syda Productions / Shutterstock
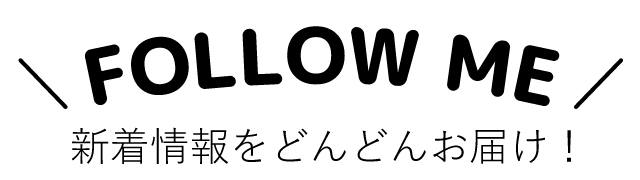



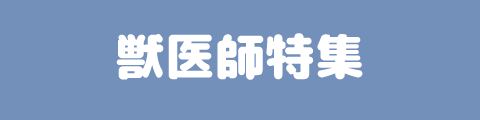







戻る
みんなのコメント